相続の手続き、どこから手をつければ良いのか分からないまま時間だけが過ぎていませんか。
ネットや動画では「自分でできる」と聞くけれど、戸籍はどこまで集めるのか、登記原因証明情報とは何か、法務局の補正連絡の意味が読めない。 そんな不安の積み重ねで、手が止まってしまう方は少なくありません。
相続登記はご自身でも進められます。 ただ、2024年4月の義務化で原則3年という期限が生まれ、小さな見落としが大きな手戻りにつながる現実があります。 「途中から頼んでも大丈夫かな」「費用はいくらくらいだろう」。 大丈夫です。
司法書士事務所LINKは、集めかけの書類や下書きのままでも引き継ぎ、ご依頼者の不安を全力で解消します。
富士市・富士宮市の方はもちろん、日本全国からのご相談に対応しています。
本記事では、義務化後に増えた“落とし穴”と回避策、そして途中からプロに任せて最短で終わらせる方法を、分かりやすくお伝えします。
 ご相談者
ご相談者相続登記って、自分でやったほうが安く済むと思ってたんですけど……やっぱり危ないですか?



実は、思ったよりも手続きが複雑で、途中でつまずく方がとても多いんです。



実際、ネットで調べながら書類をそろえたんですけど、不安になってきて……



それはよくあることですよ。この記事では、自分で進めるときの注意点や、相談すべきタイミングを詳しく解説しています。



よかった……最初から全部やり直しかと思ってました。



いえいえ。途中からのご相談でも大丈夫です。まずはこの記事を読んで、落とし穴がないか確認してみてくださいね。
本記事では、相続登記を自分でやってみたものの不安を感じている方や、途中で手が止まってしまった方に向けて、よくあるつまずきポイントや、司法書士に相談すべきタイミングなどを詳しく解説します。
- 相続登記で不安になる理由がわかる
- よくある失敗と対処法がわかる
- 司法書士と自分でやるコスパがわかる
自分で相続登記をやった人が増えている背景とは?
相続登記の義務化が進む中、「とりあえず自分でやってみよう」と思う方が増えているのには理由があります。
相続登記義務化のインパクト
2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した場合には、原則として3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。
違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
この制度改正によって、「早くやらなければ」「自分でできれば費用を浮かせたい」という考えを持つ方が増えているのです。
ネットや動画で簡単そうに見える?
「自分でできた」という体験談をブログやYouTubeなどで目にすると、自分にもできると思ってしまうのも無理はありません。
しかし、その背後には見えない苦労や知識の習得がある場合も少なくありません。
そして、相続登記のミスは必ずしもその場でわかるとは限りません。後々で相続登記のミスに気がつき、もう後戻りできないこともあります。
「費用を抑えたい」「急いでいる」に潜む見落とし
手続がスムーズに進むケースもありますが、実務では「戸籍の抜け」「書類の有効期限切れ」「登記原因証明情報の不備」など、小さな見落としが連鎖しがちです。
これらは提出のその場で発見できるとは限らず、補正対応や再収集で数週間から数ヶ月の遅れが発生することもあります。
義務化によりスケジュール感が求められる今こそ、早い段階でプロに確認する価値が高まっています。
自分でやる相続登記の流れと必要書類
「相続登記って何から始めればいいの?」という疑問にお答えすべく、一般的な流れと必要書類を整理してみましょう。
ステップごとの詳細な手順
出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める必要があります。
誰が相続人なのかを明確にするため、相続人全員の戸籍を確認します。
書類の簡略化に役立つ一覧図を作成し、法務局に提出して認証してもらいます。
相続する不動産の評価額を確認し、登録免許税の計算に使用します。
相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
相続登記には、遺産分割協議書以外にも申請書や、添付書類の作成が必要となります。
相続の内容ごとに添付する書類が異なってくるため、法的知識がある程度必要となります。
郵送または窓口提出が可能です。
書類の注意点
- 相続の内容によって様々な添付書類が必要となります。誤字脱字や記載ミスはNGです。
- それぞれの書類の期限や有効期間にも注意が必要です(例:評価証明書は年度が変わると使えなくなることも)。
よくあるつまずきポイント5選
① 書類の不備が多い
よくあるミスは、「戸籍の抜け」「古い評価証明書の使用」「登記簿の情報が最新でない」といったものです。
また、添付書類の不足により申請が受理されないケースも。
② 法定相続情報一覧図の作成で挫折
「図にするだけ」と思いがちですが、実際には正確な戸籍情報を読み解く必要があり、複数の家族構成が絡むとさらに難解になります。
また、記載方法も正確に決まっており、例えば「子」なのか「長男」なのかだけでも補正を求められます。
③ 遺産分割協議書に署名漏れや押印ミス
実印ではなかった、印影が読み取りにくく印鑑証明書との同一性を確認できないという凡ミスも意外と多いです。
④ 登記原因証明情報の理解不足
相続の場合、一般的には遺産分割協議書を添付しますが、遺言書や調停調書など、ひと言に相続と言っても
⑤ 法務局での指摘対応が難しい
補正の連絡がきても、その意味が分からず、何を直せば良いのか分からないまま時間だけが過ぎてしまう、という方が多く見受けられます。
義務化後に多い「落とし穴」5選
ケース1:書類系のミス(戸籍の抜け・年度ズレ・押印不備 など)
- 落とし穴1:戸籍の抜け。 出生から死亡までの連続性が切れていたり、改製原戸籍・除籍謄本が未収集で相続人が確定できないケースです。
- 落とし穴2:評価証明書の年度ズレ。 翌年度になると金額が更新されるため、旧年度の書類を使うと登録免許税の計算が合わず差し戻されることがあります。
- 落とし穴3:遺産分割協議書の不備。 署名漏れ、実印でない押印など、形式面の不備で受理されないことがあります。
- 落とし穴4:登記事項の表記ミス。 地番・家屋番号・不動産の表示の誤り、登記簿の最新記載と申請書の齟齬があると補正が必要になります。
ケース2:対応系のミス(登記原因証明情報/補正対応の遅れ など)
- 落とし穴5:登記原因証明情報の理解不足。 「何をどこまで書くのか」が曖昧で、相続の原因・日付・内容の特定が不十分となり、補正の対象になります。 また、法務局からの補正連絡の意味が分からず、必要書類の特定や再収集に時間がかかり、結局一度取り下げざるを得ないと言うことも。補正は珍しいことではありませんが、要旨をすばやく掴み、最短の打ち手を選べるかで完了時期が大きく変わります。
司法書士と「自分で」の比較!コスパがいいのはどっち?
コストと効果の比較表
| 項目 | 自力で対応 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 手続きの時間 | 数カ月から半年以上 | 1〜2ヶ月(個別の事情で前後します。) |
| 精神的負担 | 大きい | ほぼゼロ |
| 書類作成精度 | ミスの可能性あり | 高精度・正確 |
| 登記の成功率 | やや不安定 | ほぼ確実 |
| 総費用 | 表面は安く見えがち | やり直し防止で結果的に割安になることも |
※総費用については、登録免許税は含んでおりません。
費用は「安心への投資」
登記が完了するまでの時間や労力を考えると、司法書士への依頼費用は決して高いものではありません。
「登記をやり直すことになった」「税務上の問題が発生した」など、後からのトラブルを防げるのは大きな利点です。
よくある誤解
「全部任せないと頼めないと思っていた」「最初から依頼しないとダメだと思っていた」という声はよく聞きます。
実際には、途中まで自分で進めた書類や情報も無駄にはならず、引き継いで使えるケースがほとんどです。
\ ご相談はこちらから/
今すぐ司法書士に相談すべきサイン
相続人が遠方・多数/遺言の有効性に不安
- 相続人が全国に散らばっていて、印鑑証明や署名を揃えるのに時間がかかっている。
- 遺言書があるが、有効性や解釈に自信がない、開封の可否が分からない。
このような場合は早めにご相談ください。 当事務所は多数相続人案件の実績があり、必要書類の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税発生の場合は税理士との連携、不動産売却の場合は不動産会社の紹介など、一気通貫でサポートします。
協議が停滞・補正が続く・期限が迫っている
相続人の一部と連絡が取れない、協議がまとまらない、補正が何度も続き前に進まない、3年の期限が気になって落ち着かない。 これらは典型的な「今すぐ相談」サインです。
第三者である司法書士が入ることで、論点整理と合意形成、打ち手の優先順位付けが進みます。 必要に応じ、信頼の置ける弁護士などの専門士業を紹介することも可能です。
司法書士事務所LINKのサポート体制(富士市・富士宮市・全国対応)
無料相談の流れと準備物
初回相談は無料です。 オンライン・対面いずれも対応可能です。
事前にお持ちであれば、次の資料のコピー(写真でも可)をご用意ください。
- 被相続人の戸籍一式(ある範囲でOK)
- 相続人の戸籍・住民票等(お手元分でOK)
- 固定資産評価証明書(取得済みであれば)
- 遺産分割協議書の草案やメモ(未完成でOK)
- 現状の整理メモ(困っている点・疑問点)
「何から始めればいいか分からない」という段階でも歓迎です。
\ ご相談はこちらから/
連絡方法・対応エリア・最短目安/強み
対応エリアは日本全国です。
富士市・富士宮市にお住まいの方、出身地が富士・富士宮の方のご相談も多数承っています。
多数相続人案件の解決実績があり、複雑な相続案件や、戸籍等の書類回収の段取りに強みがあります。
また、法務局による相続未了登記の相続人調査にも協力してきた経験があり、実務の視点から「詰まりやすい箇所」を先読みして回避します。
費用は当事務所の料金ページにてご案内しています。
よくある質問
- 途中までの書類は使える?費用はいつ確定?
-
ご自身で集めた戸籍、評価証明書などは無駄になりません。
不足部分を補い、使えるものは最大限に活用します。費用の詳細は料金ページをご覧ください。 - 代理申請と本人申請の違い
-
代理申請では、書類作成から提出・補正対応までを司法書士が一括で行います。
本人申請はご自身で提出します。書類不備、補正、手続きのミスなどはすべてご自身で責任を負います。
まとめ—無理せず、「最短ルートで」確実に終わらせる
相続登記は「自分ですることもできる手続き」ですが、義務化によって時間軸が生まれた今、スピードと正確性の両立が求められます。
小さな見落としが積み重なる前に、プロを使うのが賢い選択です。
司法書士事務所LINKは、富士市・富士宮市を中心に、日本全国からのご相談に対応しています。
初回相談は無料です。
費用は料金ページで分かりやすくご案内しています。
「やりかけで止まっている」「補正が続く」「期限が不安」—
そのサインを見逃さず、今すぐご相談ください。
最短の申請ルートまで、確実にゴールまで伴走します。




- 専門家の専任担当
-
司法書士が相談から完了まで手続きをサポート致します。
- 相続・遺言・家族信託に特化した事務所
-
当事務所は相続・遺言・家族信託に特化した事務所となっております。豊富な経験でご依頼者様に最適な提案を致します。
- 豊富な相談実績
-
当事務所は開業してから700件を超える相談を受けております。その豊富な経験をから蓄積されたノウハウで高難易度の業務にも対応致します。
- 全国対応
-
オンライン面談やオンライン申請を駆使して、全国どこでも対応致します。
まずはお気軽にご相談下さい。
司法書士事務所LINKがあなたの
お悩みを解決致します。
ご相談の予約はコチラ
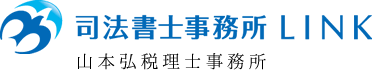
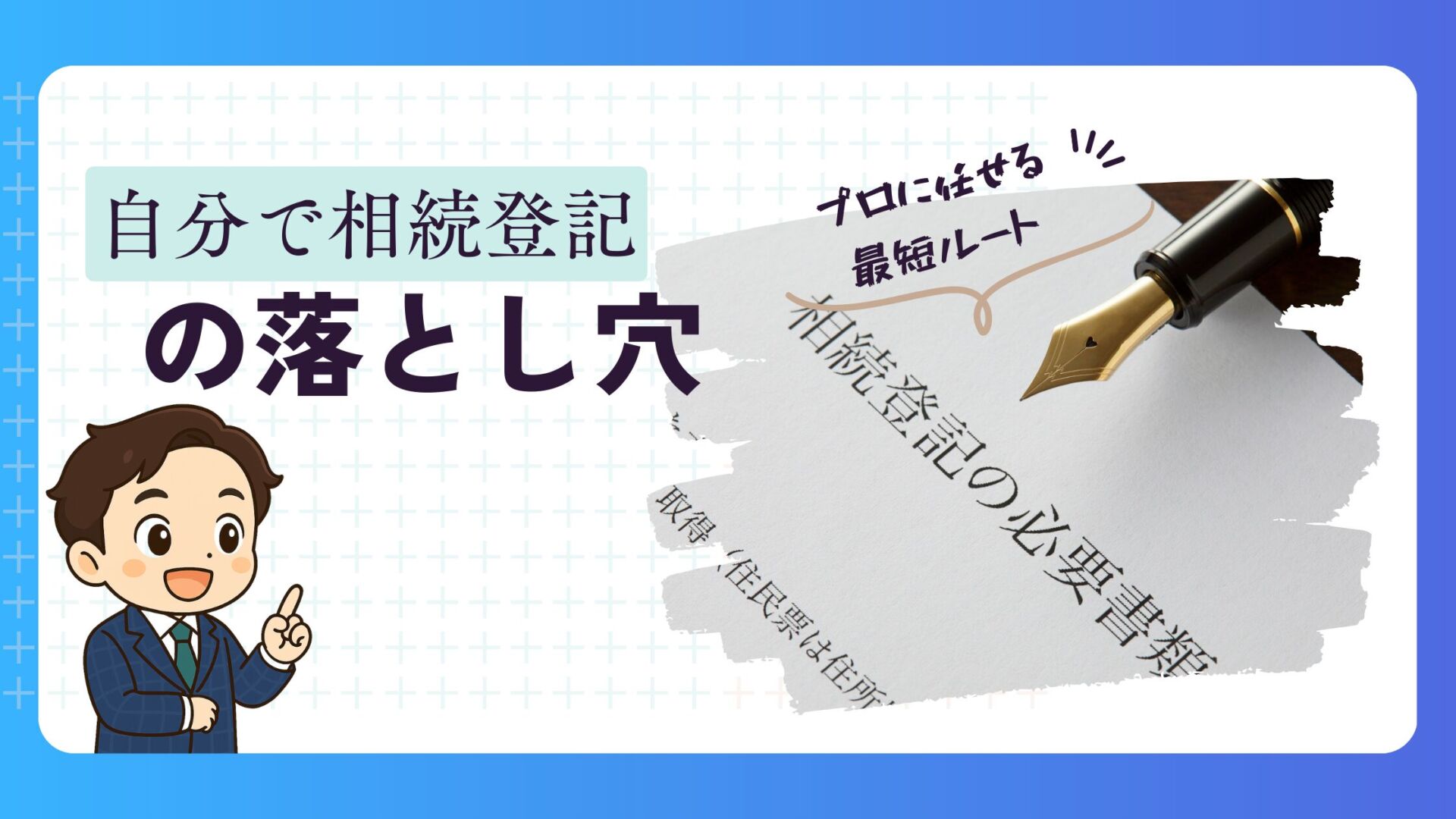



山本真吾